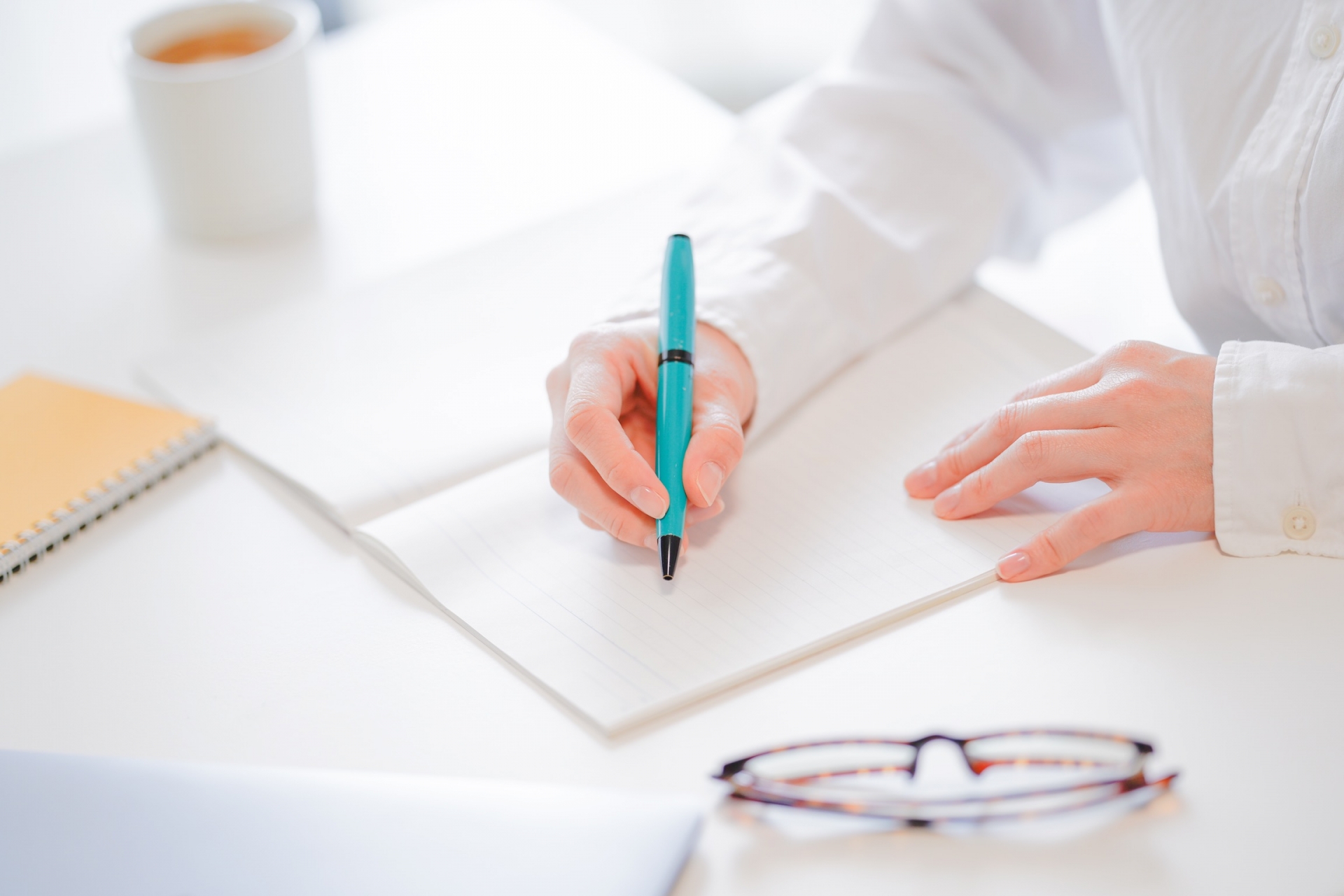新年度が始まり、子どもが中学校生活をスタートしたばかりの春──
「最近、子どもが急に無口になった」
「学校に行きたくないと言い出した」
「ちょっとしたことでキレるようになった」
そんな変化に、戸惑っているお母さんも多いのではないでしょうか。
実はこうした変化の背景には、「中1ギャップ」という現象があることをご存じでしょうか?
この記事では、不登校につながる「中1ギャップ」の正体や、思春期・反抗期の特徴、家庭教育の中で親にできる具体的な関わり方などを、最新の不登校データとともにお伝えします。
最後には、相談先として「家庭教育推進協会」のご案内もございますので、ぜひ最後までお読みください。
中1ギャップとは? 〜なぜ「中学で変わる」のか〜

「中1ギャップ」とは、小学校から中学校への進学時に、学習環境や人間関係の急激な変化に適応できず、心身に不調をきたす現象をいいます。
授業は教科ごとに先生が変わる
通学距離が長くなる
部活動が始まる
人間関係が一新される
宿題やテストの頻度が増える
これらの変化が子どもにとっては大きなプレッシャーになります。
特に内向的な性格や、頑張り屋さんタイプの子ほど「自分なりに頑張っていたのに、うまくいかない…」という挫折感を抱きやすく、結果として登校しぶりや不登校に発展するケースが少なくありません。
思春期と反抗期の交差点で起こる心の混乱

中学入学の時期は、心と身体の急成長を迎える思春期とも重なります。
感情が不安定になる
自己主張が強くなる
親の干渉を嫌がる
他者との比較に敏感になる
「なんでそんなに怒るの?」
「急に反抗的になった」
それは親にとって“困った変化”に見えるかもしれませんが、実は「自分で考えたい」「自分の人生を自分で選びたい」という“成長の一歩”でもあります。
親がこの時期に必要以上にコントロールしようとすると、逆に子どもは心を閉ざしてしまい、登校しぶりや家庭内での暴言などに繋がることもあります。
不登校の最新データに見る「中学1年生の壁」

文部科学省が発表した令和4年度「児童生徒の問題行動・不登校調査」によると、中学生の不登校児童生徒数は全国で約13万人にのぼります。
中でも中学1年生の不登校者数は突出しており、入学直後の5月から6月にかけて一気に数が増える傾向にあります。
学校の雰囲気に馴染めない
人間関係のトラブル
学業不振による自信喪失
親からの過度な期待やプレッシャー
つまり、「中1ギャップ」は、不登校のきっかけになりやすい要因が重なる時期でもあるのです。
「自己効力感」を育てる家庭の関わり

子どもが「学校に行きたくない」と言い出したとき、親は焦って「なんとか行かせよう」としてしまいがちです。
でも、そこで大切なのは、「自己効力感」=“自分はできる”という感覚をどう育てるか。
自己効力感が下がっている子どもほど、「失敗したらどうしよう」「また怒られるかも」と不安が先に立ち、学校に足が向かなくなってしまいます。
小さな成功体験を積ませる(例:1日5分だけ勉強、1日だけ登校など)
「できたこと」をフィードバックする(例:「今日は朝起きられたね」「話せてうれしかった」)
失敗しても責めない(例:「チャレンジしたことがすごいね」)
家庭が「失敗しても受け入れられる場所」になることが、子どもの再起の力を育てます。
「自立」と「自律」の違いに気づくこと
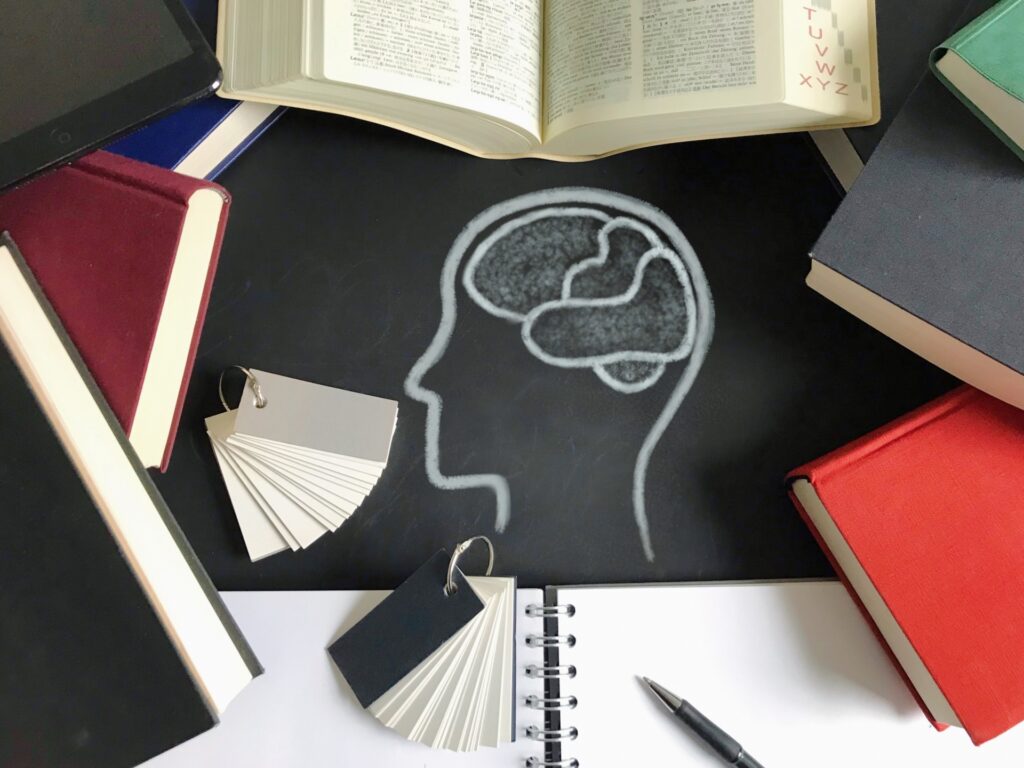
よく「うちの子にも早く自立してほしい」と言われますが、実はそれ以上に大切なのが自律です。
自立
経済的・生活的に他人に頼らずに生きること
自律
感情や行動を自分でコントロールすること
不登校の子どもに求められるのは、すぐに学校に行くことではなく、「行けない自分を責めずに、少しずつ立て直していく力」──つまり自律の力です。
感情を言葉で表現する練習
自分で考えて選ぶ場面を与える(例:「今日は午前だけ行ってみる?」)
結果ではなく過程を認める声かけ
中1ギャップのつまずきは「高校生」への成長の土台になる

中1で不登校になったとしても、その後、高校生になって元気に通っている子は大勢います。
子どもたちは、一度止まっても、時間をかけて力を蓄え、また歩き出す力を持っています。
親にできるのは、今すぐ答えを出そうとせず、子どもの内面の成長を信じて待つこと。
そして、日々の家庭教育の中で「自分を大切にする感覚」「人と関わる力」「感情との付き合い方」を少しずつ身につけていくことが、次のステップに繋がるのです。
今、できる一歩を一緒に考えませんか?

「中1ギャップで不登校になった」
「反抗期で全く話を聞いてくれない」
そんな悩みを、ひとりで抱え込んでいませんか?
私たち家庭教育推進協会では、思春期の子どもとの関わり方や、不登校の子どもを支える家庭での接し方について、公認心理師や不登校専門のカウンセラーによる相談・サポートを行っています。
焦らず、比べず、責めずに。
親としてできることを、いっしょに見つけていきましょう。